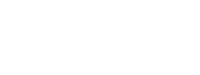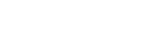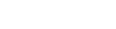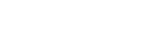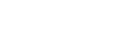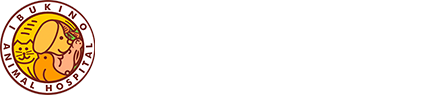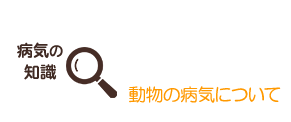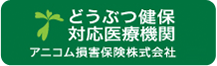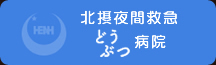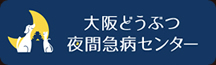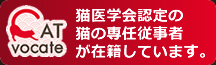- TOP
- 動物病気コラム
FIP(猫伝染性腹膜炎)の症状と原因・治療について|獣医師が解説|大阪府和泉市のいぶきの動物病院2024年02月22日
大阪府和泉市、堺市、大阪市、岸和田市、泉大津市の皆さまこんにちは。 大阪府和泉市のいぶきの動物病院、院長の島田です。 今回は猫伝染性腹膜炎(FIP)について解説いたします。 1.FIP(猫伝染性腹膜炎)とは? 猫コロナウイルスが、原因となり、腹部の臓器を包んでいる腹膜や目や神経に炎症を起こす疾...
猫の口腔内腫瘍「口の中のがん」について|獣医師が解説|和泉市のいぶきの動物病院2024年02月21日
和泉市、堺市、岸和田市、泉大津市、高石市の皆さんこんにちは。和泉市のいぶきの動物病院です。今回は、猫の「口の中のがん」についての病態や症状、治療方法について解説をいたします。 「愛猫の食べ方が変…」「最近、よく口を気にするな…」という場合には、口の中に腫瘍が存在する可能性もあります。...
犬の外耳炎の原因や症状、治療方法について|獣医師が解説|和泉市のいぶきの動物病院2023年08月11日
耳垢検査 和泉市、堺市、岸和田市、泉大津市、高石市の皆さんこんにちは。和泉市のいぶきの動物病院です。今回は、犬の外耳炎の原因や症状、治療方法について解説をいたします。 犬の耳の汚れや臭いって病気? 耳垢が多く、臭いのする耳は何らかのトラブルが起きている可能性があります。ワンちゃんの耳は本来が皮膚の延...
デンタルセミナー開催決定2021年10月16日
みなさんこんにちは。 いつの間にか、季節はすっかり秋模様となって参りました。 飼い主様・ペットちゃんの体調はいかがでしょうか。 さて今回は第2回デンタルセミナーの開催が決定しました! 11月23日(火)祝日です。 皆様の愛犬・愛猫ちゃんのお口の匂いはどうですか? 匂いはきつくないですか? 歯周病は犬...
東日本大震災から10年2021年03月09日
3月11日、東日本大震災から10年になります。 もう10年も経つのかと思います。 発生時、手術時間中でした。ニュースで津波押し寄せ、多くの建物が流される映像が流れ 「これは大変なことが起こった」と思いました。 実際、1万5,899人の方が亡くなられ、今も2,527人の方が行方不明です。 福島...
東日本大震災から10年2021年03月09日
3月11日、東日本大震災から10年になります。 もう10年も経つのかと思います。 発生時、手術時間中でした。ニュースで津波押し寄せ、多くの建物が流される映像が流れ 「これは大変なことが起こった」と思いました。 実際、1万5,899人の方が亡くなられ、今も2,527人の方が行方不明です。 福島の原発事...
ドクターズケア(療法食) 価格改定のお知らせ2021年03月08日
当院では、ドクターズケア(療法食)の価格改訂を2021年4月1日(木)に実施します。 原材料などの高騰のため、メーカー価格が改定される運びとなりました。 新価格は、当院までお問い合わせください。 ご理解の程、お願いいたします。 *黄色いパッケージのドクターズダイエット(総合栄養食)は、価格改定の対象...
ドクターズケア(療法食) 価格改定のお知らせ2021年03月08日
当院では、ドクターズケア(療法食)の価格改訂を2021年4月1日(木)に実施します。 原材料などの高騰のため、メーカー価格が改定される運びとなりました。 新価格は、当院までお問い合わせください。 ご理解の程、お願いいたします。 *黄色いパッケージのドクターズダイエット(総合栄養食)は、価格改定の対象...
ウェルニャス2021プロジェクト②2021年01月23日
こんにちは。看護師の寺坂です。 寒い日が続きますが、猫ちゃんたちの体調に変化はございませんか? 今回は1月上旬にご案内させていただいた猫ちゃんのシステムトイレ“toletta”を我が家の猫たちで使ってみた感想をお伝えします。 トレッタ撮影動画 ↑↑↑↑こちらをクリックしてみて╰(*´︶...
ウェルニャス2021プロジェクト②2021年01月23日
こんにちは。看護師の寺坂です。 寒い日が続きますが、猫ちゃんたちの体調に変化はございませんか? 今回は1月上旬にご案内させていただいた猫ちゃんのシステムトイレ”toletta”を我が家の猫たちで使ってみた感想をお伝えします。 トレッタ撮影動画 ↑↑↑↑こちらをクリックしてみて...